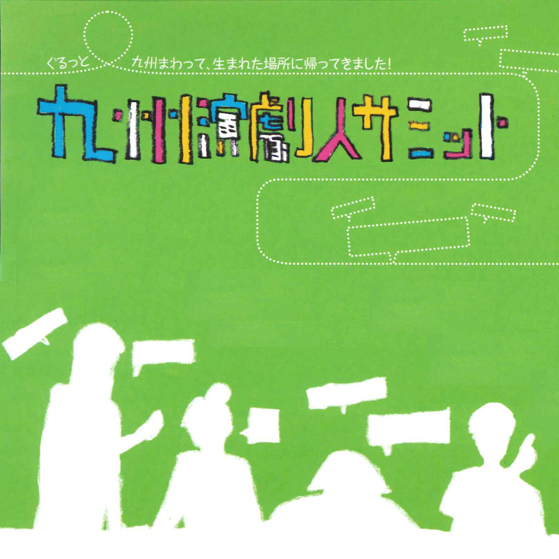2012.05.06
福岡は、5月の3,4日と、博多どんたく港まつりでした。歴史は長く、今年で833年目とのこと。博多どんたくが一段落して夏がやってくると、ぽんプラザホールのご近所である櫛田神社を中心に、福岡、博多は7月15日の博多祇園山笠に向かって突き進みます。
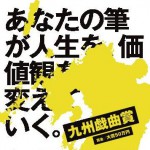 九州地域演劇協議会が主催している「九州戯曲賞」は、今年、この二つの祭りを挟みこむようにして実施されます。この3点を結ぶ共通点を敢えて見出そうとすると、「明太子をつくってよかった」でおなじみの味の明太子ふくやです。「九州戯曲賞」は設立当初から株式会社ふくやからの協賛をいただいています。地域文化への理解が深い地場企業があるということは非常にありがたいことであります。
九州地域演劇協議会が主催している「九州戯曲賞」は、今年、この二つの祭りを挟みこむようにして実施されます。この3点を結ぶ共通点を敢えて見出そうとすると、「明太子をつくってよかった」でおなじみの味の明太子ふくやです。「九州戯曲賞」は設立当初から株式会社ふくやからの協賛をいただいています。地域文化への理解が深い地場企業があるということは非常にありがたいことであります。
九州戯曲賞は、2009年から始め、今年で4回目となります。2012年5月15日消印有効となっています。締め切りまであまり間が無いですが、まだ間に合う日程です。もし、身近に九州の劇作家がいらっしゃいましたら、お勧めしてみてください。今回の最終審査は、九州出身の第一線で活躍する劇作家の5名、岩松了、中島かずき、古城十忍、横内謙介、松田正隆(敬称略)にお願いしています。
さて、福岡の演劇状況です。公演カレンダーを見てみると、毎週末何かしらの公演がどこかであっているようです。私が学生をやっていた15年くらい前の公演数は随分と少なく、楽しみにできる公演も年に数回という感じでした。演劇を志す多くの若者は東京を目指し、演劇を続ける場合は、どこで続けるかということを否が応にも考えなければいけなかったのかなぁと思います。私の高校演劇での仲間はやはり東京へ行き、その反発かはわからないけれど、東京の演劇シーンをろくに調べようとせず、私は絶対東京には行くものかと思ったものです。
今では福岡の演劇公演も随分と増え、年に数回ではあるけれど、公演を「選ばなければならない」という贅沢も味わえるようになりました。一方で、少子化のことも考えると、普通にやっていると、この先劇団は増えにくいのではないのかなぁと予想されます。大学演劇部は合同公演などを通して、卒業後に劇団を旗揚げするという現象が戻りつつありますが、高校の演劇部は最近元気がないと聞きます。将来の年代格差を防ぐ意味でも、これからの若い世代に対して、現役の私達が有効にアプローチできる方法を探さないといけません。
遠い未来の私たちの子孫が振り返った時に、833年とは言わなくても、長い歴史があるらしいと自慢できるものの一端でも担えたら素敵です。そういう歴史を作れるのは、文化に他ならないと思います。まぁ、そう言った心持ちでやっていると、壮大かなぁと思うわけです。
文:本田範隆(九州地域演劇協議会 前理事長)|NPO法人FPAP
2012.04.30
「サミット」ってよく耳にする言葉ですけど、そして何となく「首脳会議」のことだと思い込んで使っていたんですけど、改めて調べてみると「山頂」っていう意味なんですね。各国の首脳陣を山頂に準えて、ということだったのか。
2005年に熊本で開催された日本劇作家大会のイベントのひとつとして「九州演劇人サミット」は産声を上げました。九州各地域の演劇人や、九州出身の劇作家・演出家の方々が一堂に会して、それぞれの地域の演劇事情について話したり、地方ならではの、いままさに直面している問題について討議をし、中央で活動する先人の意見をうかがったりしました。「各地の演劇人が一カ所に集う」という、この単純明快・いたってシンプルなイベントが生み出した熱量は、想像をはるかに上回る盛り上がりと手応えを感じたことを思い出します。そして第2回サミットの福岡開催の話へトントン拍子に運んだように記憶しています。
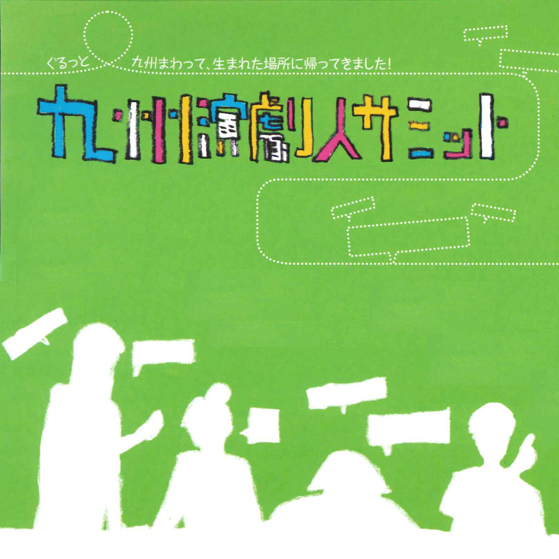 その後、第3回・長崎、第4回・宮崎、第5回・佐賀、第6回・鹿児島、第7回・大分…と一巡り。開催地域によって、さまざまな関連事業も行われました。演劇ワークショップ、ワークショップ参加者やパネリストによる出し物など毎回趣向を凝らした内容で、大いに賑わいました。と同時に、そのそれぞれのイベントから各県の演劇シーンの動向なども垣間見えて、とても興味深いのです。この県はこんなタイプの演劇が今主流なんだなぁとか、独自の地域性だったりとか、「へぇ!そうなんですか!?」と驚くこともしばしばです。
その後、第3回・長崎、第4回・宮崎、第5回・佐賀、第6回・鹿児島、第7回・大分…と一巡り。開催地域によって、さまざまな関連事業も行われました。演劇ワークショップ、ワークショップ参加者やパネリストによる出し物など毎回趣向を凝らした内容で、大いに賑わいました。と同時に、そのそれぞれのイベントから各県の演劇シーンの動向なども垣間見えて、とても興味深いのです。この県はこんなタイプの演劇が今主流なんだなぁとか、独自の地域性だったりとか、「へぇ!そうなんですか!?」と驚くこともしばしばです。
サミットの後は、交流会もあります。パネリスト、地元演劇関係者、参加者(ワークショップ参加者、観客も含みます)でごった返す交流会は壮観。新しい出会いあり、サミットでは語られなかった裏情報?やさらに突っ込んだ議論が展開されることあり!尽きない演劇トークの応酬の中、夜は更けていくのです。
九州を一周したサミットは、前回の第8回で福岡に舞い戻り、次回はサミットの生まれた場所熊本に帰ってきます。一周して見えてきた九州の演劇シーン。今度の熊本サミットでは、「地域演劇人」の立場から「表現者視点からの地域演劇観」に少し深く突っ込んでいけたらと考えています。県を跨いだ合同公演や年代別の地域演劇論をテーマに、5人のパネリストと熊本の若手演劇人の間で熱いトークが繰り広げられることを今から楽しみにしています!
九州にもたくさんの演劇人という名の「山頂」が居て、それがこのサミットを通して繋がり「山脈」を成して行く。そんな九州演劇山脈を、九州圏内だけでなく全国から観に来てもらえるような、面白いイベントになっていけばいいですね!
文:河野ミチユキ(九州演劇人サミットin熊本コーディネーター)|熊本演劇人協議会
九州演劇人サミットin熊本
それぞれ活動していた九州内の地域演劇に、
ゆるやかなネットワークができ、
その延長線上に九州地域演劇協議会は設立されました。
九州各地で活躍する演劇人が一堂に会し、
演劇活動の現状・課題・展望などを共に語り合う場として年に一度開催している、
「九州演劇人サミット」も各県持ち回りでスタートし、7県全てを一巡しました。
より新鮮な話題を定期的に発信していくため、
本サイトで、各県持ち回りによるコラムを配信したいと思います。
九州の演劇シーンを垣間見られるような内容になれば幸いです。
(九州地域演劇協議会事務局)
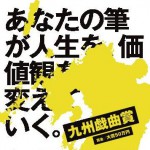 九州地域演劇協議会が主催している「九州戯曲賞」は、今年、この二つの祭りを挟みこむようにして実施されます。この3点を結ぶ共通点を敢えて見出そうとすると、「明太子をつくってよかった」でおなじみの味の明太子ふくやです。「九州戯曲賞」は設立当初から株式会社ふくやからの協賛をいただいています。地域文化への理解が深い地場企業があるということは非常にありがたいことであります。
九州地域演劇協議会が主催している「九州戯曲賞」は、今年、この二つの祭りを挟みこむようにして実施されます。この3点を結ぶ共通点を敢えて見出そうとすると、「明太子をつくってよかった」でおなじみの味の明太子ふくやです。「九州戯曲賞」は設立当初から株式会社ふくやからの協賛をいただいています。地域文化への理解が深い地場企業があるということは非常にありがたいことであります。